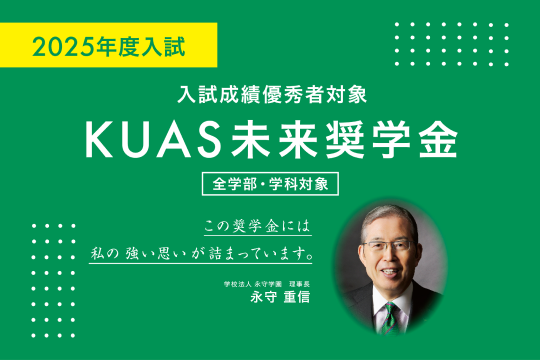人とともに多様な生き物が共存できる環境、
バイオ環境の実現を目指す。
地球温暖化や食料問題の解決が急がれる今、人と共に多様な生き物が共生できる環境“バイオ環境”の実現は、世界共通の目標となっています。バイオ環境学部では、これらの問題に対して基礎から応用に至る幅広いアプローチを可能にするために必要な知識と技術を学ぶことで、持続可能な生命・食料・農業・環境の実現に貢献できる人材になることを目指します。

[こんな人におすすめ]
- 環境の保全や再生に興味がある
- 豊かな自然をフィールドにして学びたい
- 生物技術者や環境デザイナーをめざしている
- 水質分析・環境管理技術者をめざしている
- 理科教員・公務員をめざしている
[こんな人におすすめ]
- 生物の持つ能力を使って健康、医療に貢献したい
- 食品のことを深く学んで食品業界で活躍したい
- 植物・微生物の力で食料問題や環境問題を解決したい
- 理科教員になりたい
- グローバルに活躍できる研究者をめざしたい
Pick Up
ピックアップ
国際コース 2025年9月新設
国際コースの設置により日本人学生と留学生が交流する国際環境を提供し、企業での研修・研究などのプログラムも用意します。
スマートアグリハウス(2024年3月竣工)
バイオ環境館の隣に、亀岡市、亀岡商工会議所と連携して産学公連携拠点を整備します。複合環境制御システムを導入したスマートアグリハウスでは、養液栽培技術を用いた野菜類の研究開発や実証研究を行います。
News
ニュース
施設紹介

新種苗開発センター

圃場

食品開発センター

バイオ環境館

微生物培養室

様々な分析機器
Policy
教育ポリシー
教育目的
環境問題や資源・エネルギー問題の本質的な解決を図るため、バイオサイエンス分野の先端研究の成果や技術を生かし、国際連携や地域との協力のなかで「人とともに多様な生き物が共生できる環境(バイオ環境という)」を実現することができる人材を養成する。
卒業認定・学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)
バイオ環境学部は、生命、食、環境、農業に関する実学的教育を通じて、グローバル化社会において自らの力で生き抜き、社会に貢献し続ける社会人の育成を教育の目的とします。
1.知識・理解
1.1 生命、食、環境、農業に関する知識体系を他領域の知識と関連づけながら修得し、変容するグローバル社会の諸問題を解決するために活用できる。
2.技能
2.1 生命、食、環境、農業に関する技術を実験・実習・フィールドワークを通じて習得し、それらの技術を用いて、必要な情報を収集し、活用できる。
2.2 多様な言語を用いて、他者と意思疎通を行うことができる。
3.思考・判断・表現
3.1 生命、食、環境、農業に関して、修得した知識、技能ならびに経験を活かして、複眼的思考で自らの考えを論理的に組み立て、表現できる。
3.2 上記分野に関して自らが主題を設定し、文献調査、実験等で収集した情報に基づき、論理的・客観的・批判的な分析と考察ができる。
4.関心・意欲・態度
4.1 生命、個体、集団、自然に対して、環境と調和という意識を持ち、変容するグローバル社会の諸問題に継続的に関心を示し、専門技能と変化に対応できる専門知識・教養で、その問題の解決のために粘り強く主体的に行動できる。
4.2 多様な他者と協働しながら、自律的な社会人として行動できる。
教育課程編成・実施の方針(カリキュラム・ポリシー)
1.教育課程編成
1.1 現代リベラルアーツ科目および生命と食、環境と農業の分野からなる基礎科目、専門基礎科目を学修することによって、柔軟に思考し、多角的に事象を見て、的確な判断を下すことができる力を育成します。
1.2 生命と食、環境と農業の分野からなる専門基礎科目および専門科目(専門知識と専門技能)を学修させ、多角的に真理を探究する力を育成します。
1.3 専門科目(専門知識と専門技能)を学修後、専攻演習・卒業研究を通じて、問題解決を導く力を育成し、人々の生活の向上と人間社会の発展に貢献しようとする姿勢を養成します。
1.4 日本人学生は英語を、留学生は日本語を中心とした多様な言語力を発展させることで、上記の能力に対応できることを目指します。
2.学修方法・学修過程
(学修方法)
2.1 4 年間の教育課程では、教養科目や専門科目を理論的に学修するだけでなく、実験・実習およびキャリア学修も連動させながら実践的かつ能動的に学修します。
(学修過程)
2.2.1 基礎科目、専門基礎科目および専門科目としての実験・実習を通じて、コミュニケーション力、協働力、課題発見力やリーダーシップを育む学修を行います。
2.2.2 専攻演習・卒業研究を通じて、コミュニケーション力、協働力、課題発見力をさらに高め、また行動力や論理的思考力を育む学修を行います。
2.2.3 卒業研究を通じて、そのテーマを追求すること、自己を管理することを身に付けます。
2.2.4 卒業研究やその他実習科目などでの地域との連携を通じて、社会の一員として、社会の発展に積極的に関与できる力を育む学修を行います。
2.2.5 卒業研究を通じて、その関連する分野の知識を自主的に学修し、研究課題の解決を図る力を育む学修を行います。
3.学修成果の評価
3.1 学修成果は、ディプロマ・ポリシーで定められた能力と、カリキュラムの各科目で設定される到達目標の達成度を示すものであり、アセスメント・プランに従って多様な方法で学修成果を評価します。
3.2 各科目の内容、到達目標、および評価方法・基準をシラバスに示し、到達目標の達成度を評価します。
入学者受入れの方針(アドミッション・ポリシー)
本学部の教育目的に即した人材を育成するために、本学部の教育目的を理解し、意欲と主体性をもって勉学に励むことができ、高等学校の教育課程で修得する基礎的な学力とそれを活用する力、他者とのコミュニケーション能力を備える人を求めます。
1.知識・技能
・高等学校で履修する科目についての基礎的な知識・技能を持つ。
2.思考力・判断力・表現力
・自然や自然の現象について考え判断する能力があり、自分の考えを表現できる。
3.主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度
・学問を主体的に学ぶ強い意欲を持つ。
・実践的な課題に対して、多様な人々と協働して取り組める。
・国際人としての教養を身につけ、日本人学生は英語を、留学生は日本語を中心とした多様な言語力の向上を目指す意欲を持つ。