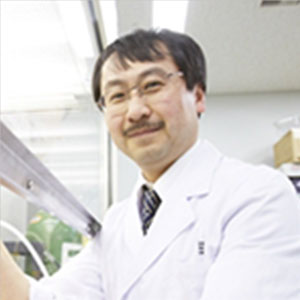食品 ~おいしいプラスαを学びたい~


坊 安恵 講師

食文化の継承と食の創造
日本には地域に根付いた多様な食文化があります。この食文化は、地域の気候風土、農林水産業といった地域の産業、生活や文化と密接な関係を持っており、日本の各地には地域独自の食文化があります。しかし、現代では、社会のグローバル化が進展する中で、世界中で同じ食事ができるようになりました。また、以前は、地域ごとに特徴のあった農産物(例えば、伝統野菜)が在来種で栽培・生産されていましたが、近年では、F1品種など育成栽培の展開により在来種が淘汰され、統一化された野菜が栽培・生産されるようになり、日本のどこでも均一性のとれた野菜を調理・加工するようになっているのが現状です。このことから、日本にある多様な食文化は均一化されたことで、地域の食文化は継承の危機に直面しています。
各地域の気候風土と調和した先人の生きる知恵と経験の産物であり、次世代に継承すべき伝統文化の1つである食文化の変遷や継承について農泊、農家民宿、農家レストラン、地域の6次産業化などに焦点を当て、研究しています。また、地域の食文化を継承するだけでなく、新たな食の創造の動きについても注視しています。
機能性分子をみつけて新食品開発へ
食品の持つ生理機能を解明して機能性食品を開発
食品の機能性の中でも、高血圧や糖尿病、脂質異常症や肥満と言った生活習慣病と言われる病気を改善できるような食品の研究を行っています。食品の素材としては、京野菜をはじめとして、普通にスーパーで売られているような野菜もターゲットにして研究しています。すでに強力な生理機能を示す食品素材も見つけていますが、その食品の中でどのような物質がその活性を示すのか、いろいろな分析装置を使用して解明したり、さらには動物を使って実際にそのような生理機能が得られるのか、検討しています。ただ、このような研究は、単独の研究室ではできないので、宮崎大学、京都大学、北海道大学、神戸女子大学、等の先生方とも共同研究させて頂きながら進めています。食品にはまだまだわからない機能が隠れている宝の山とも言えます。皆さん、一緒にそれを探してみませんか?

四日 洋和 講師


食べられるのに捨てるなんてもったいない
京野菜は地域野菜のブランドとして高い評価を受けていますが、一方で、収穫した野菜の3割ほどは、形や大きさが流通の規格に合わないなどの理由で廃棄されているのが現状です。しかし、これら廃棄野菜も貴重な食資源であることには違いはなく、現在、実用的な解決策が求められています。当研究室では、6次産業化の推進を目的として、『京野菜加工のトリセツ』というプロジェクトを立ち上げ、廃棄野菜の粉末化に関するデータベース開発を行っています。
野菜の粉末化とは、野菜を乾燥し粉砕するだけのシンプルな加工です。しかし、シンプルですが奥が深く、経済的な値段で高品質な野菜粉末を作製するためには、乾燥方法の選択やその操作条件の検討など、専門的な知識と技術が必要となります。特に、糖度の高い作物や、抗酸化成分や香り成分を多く含む作物の粉末化においては顕著です。また、食品開発では、技術性や経済性のみならず、食品関連分野の法律も考慮した加工プロセス設計が要求されます。このように、食品加工では分野を超えた専門知識が要求されるため、6次産業化の推進にはデータベースの構築が極めて重要となります。プロジェクトでは、廃棄農産物ゼロの社会を目指して、地域と連携して『生産×加工』の可能性を追求しています。