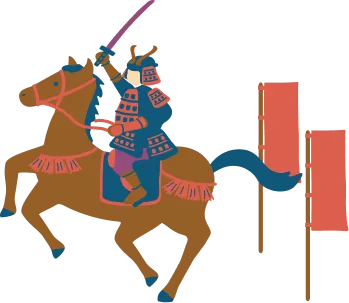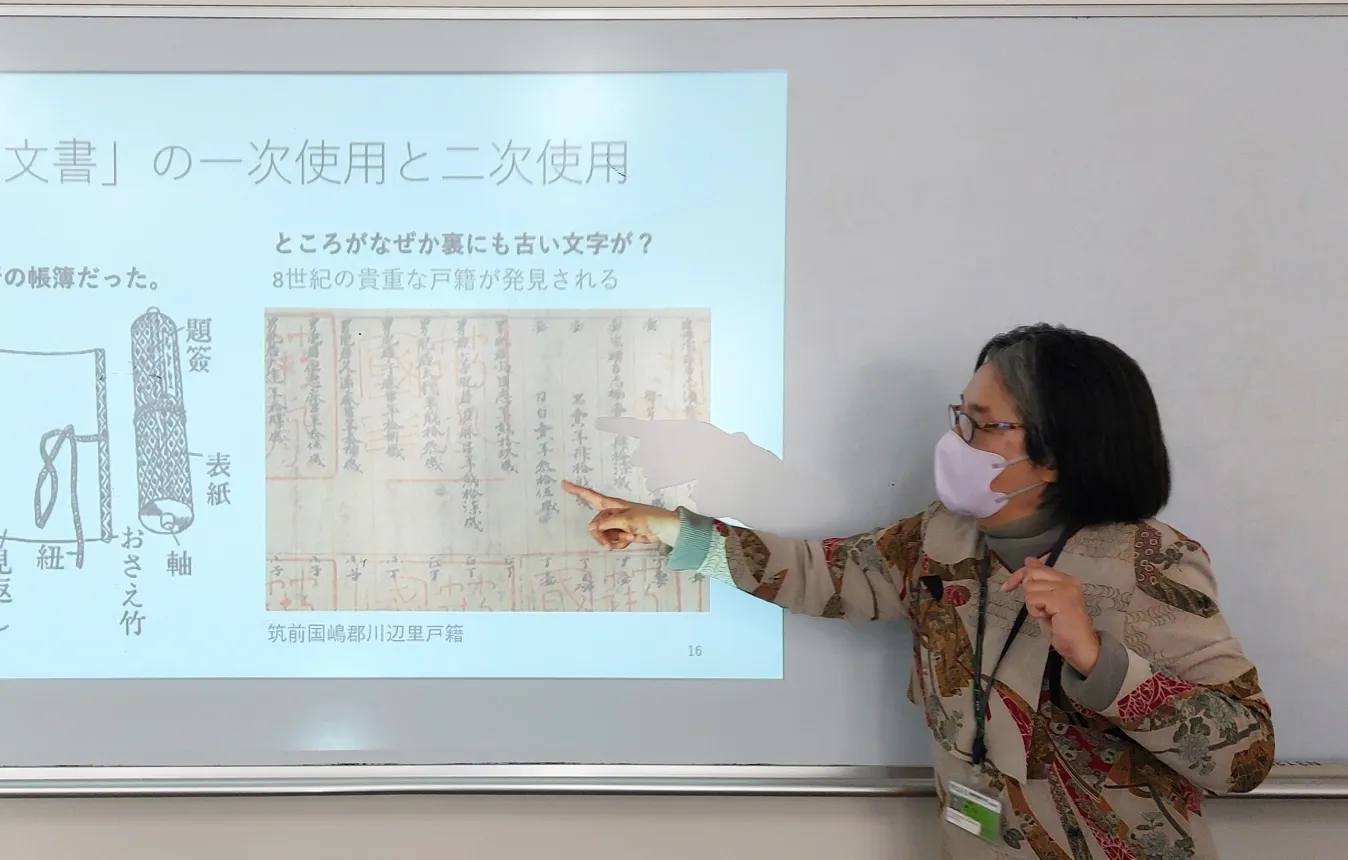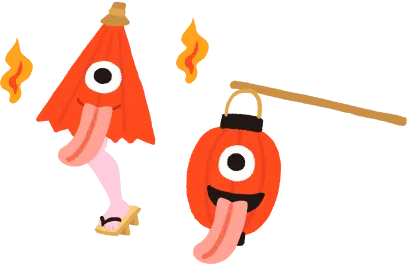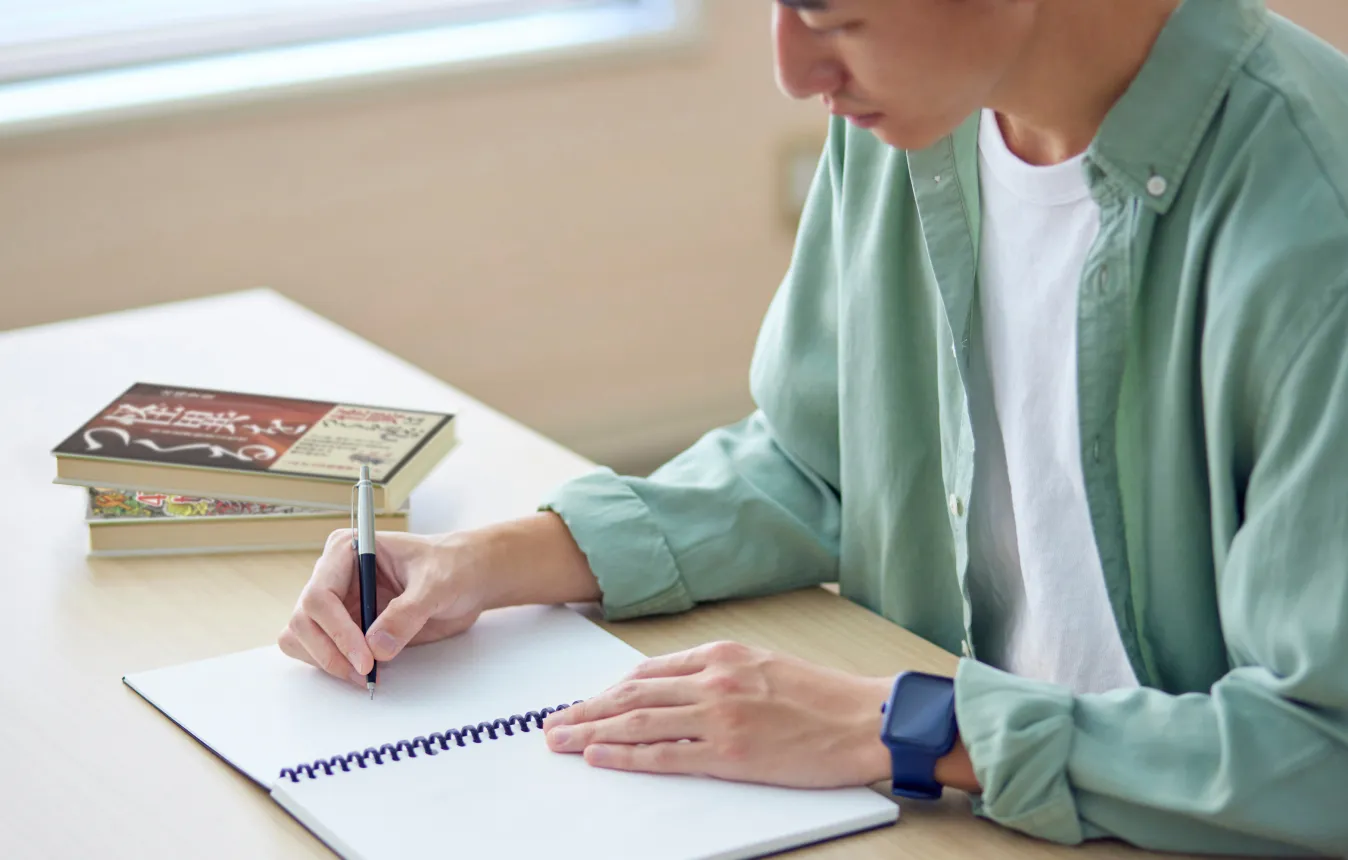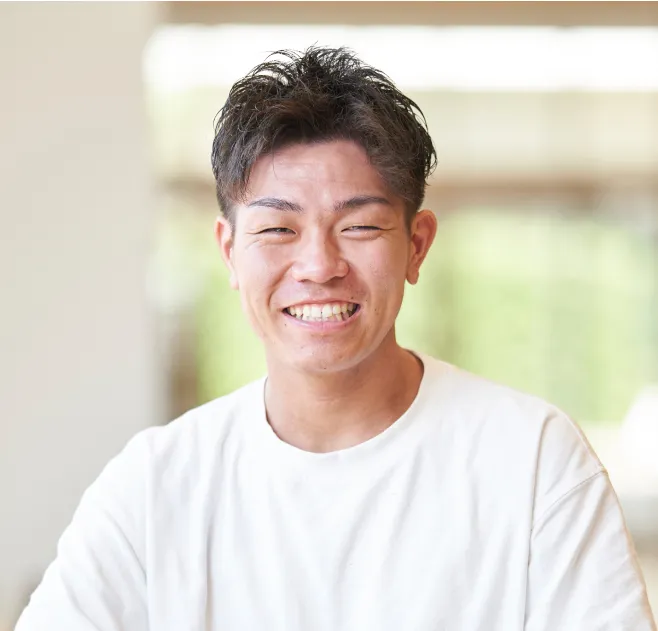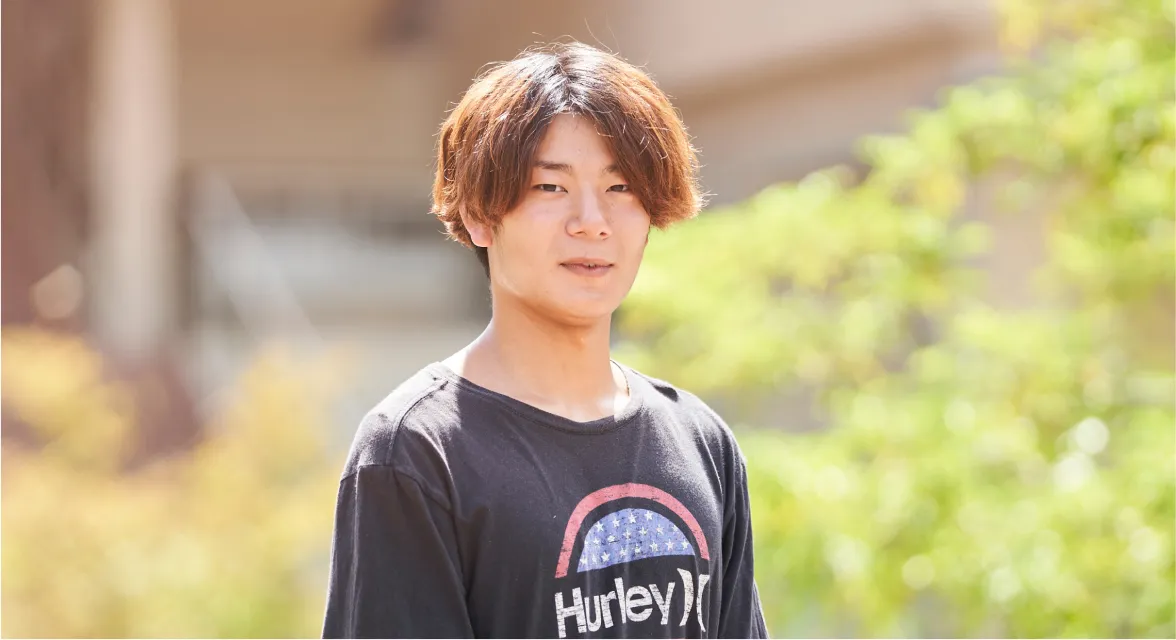フィールドワーク演習Ⅰ・Ⅱ
京都の歴史や文化がギュッと詰まった
イベントに入り込んで学ぶ!
亀岡祭を地元の方と
一緒に盛り上げる
歴史文化学科の中で学ぶ民俗学は、地域のお祭りや文化活動に参加して、観察し、お話を聞き、記録して分析する学問です。フィールドワーク(参与観察や聞き書き)の一環として、毎年10月に行われる亀岡祭には、3年生と2年生がチームになって参加します。実際の祭りの熱気と面白さを感じながら、祭りへの理解を深めます。

一度途絶えてしまった
伝統の筏を復活!
トロッコに乗って嵐山から保津川を眺め、船に乗って下るルートは観光客に人気です。実はこの保津川(大堰川)はずっと昔、平安京が興る前から材木を筏(いかだ)にして運んでいました。しかし、近代化により昭和30年に途絶えてしまうことに。
フィールドワーク演習では、筏をくみ上げ操縦する筏士(いかだし)さんにお話しを聞きし、昔ながらの12連筏を復活させるプロジェクトの運営や記録を担当しています。