11月16日(土)、本学太秦キャンパスのみらいホールで、「白書で学ぶ現代日本」の公開講演会「日本経済の現状と課題 -『令和6年度経済財政白書』を中心に-」が開催されました。
第1部では、内閣府の荻野秀明氏が、『令和6年度経済財政白書』の解説を中心に「日本経済の現状と課題」について講演。
白書第1章「マクロ経済の動向と課題」については、日本の実体経済の動向として2023年度の名目GDPが過去最高水準となった一方で、実質ではマイナスとなり、インフレ率を下回る所得の伸びにとどまったことや日本の労働市場の特徴的な動きとして、過去10年間を通じて生産年齢人口が減少する中にあって、女性の正規・非正規の雇用の拡大により雇用者数の増大が実現されてきたこと。さらに、過去2年間を見ると、29歳以下の若年層での賃上げ率が最も大きく、年齢階級が上がるほど賃上げ率が低くなる傾向が確認された一方、消費のピークは50歳台であることから、この年齢階級の賃上げ率の低さが日本のマクロ消費の停滞を説明する要因の一つであることが指摘されました。
白書第2章「人手不足による成長制約を乗り越えるための課題」では、労働市場のマッチング効率性の国際比較データから、米国やドイツとの比較では日本のマッチング効率性が低く、具体例として、求人数と失業者数が同数の条件下では、1か月以内に失業者が雇用に結びつく割合は米国の80%に対して日本は30%程度と大きく下回ることが示されました。また、日本の職種別求人倍率については、AIを含むIT化の進展により求人数が減少している事務職の求人倍率が0.4程度と非常に低いのに対して、建築、介護、運転などの職種では大きな人手不足の状態であるため、職種間でのミスマッチを解消するための労働移動の促進が重要であると指摘。日本の人手不足を補充する役割が期待される外国人労働者については、依然として日本人労働者との賃金格差が大きいものの、学歴、年齢、勤続年数、性別などの労働者の属性を揃えた場合には7%程度に賃金格差が縮小することが確認されたと説明がありました。また、在留資格別では高技能人材の格差は低く、技能実習資格になると職種に関係なく大きな格差が存在することが示されました。
最後に、白書第3章「ストックの力で豊かさを感じられる経済社会へ」では、日本の家計の金融資産投資構造の現状として現預金への大きな偏りが確認される一方で、若年層や高所得世帯ほど、株式等のリスク資産での運用が増加傾向にあり、政府が掲げる「貯蓄から投資へ」の動きを促進するためには、家計の所得上昇が重要であると説明。また、高齢者の就業の現状として、主要先進国の中で日本の高齢者の労働参加率は男女ともに目立って高い水準にあるが、その背景には所得や資産の不足を補うための就労ではなく、働くことそれ自体に高い意欲を示していることが確認されました。一方、企業から見た高齢者雇用の課題としては、労働時間が長い運輸や宿泊などの業種では「健康上の配慮」を、人手不足感が相対的に低い製造業などの業種では「生産性の低下」を挙げる割合が高く、そうした課題の解決・緩和に有効な措置を積み上げることが高齢者の知識と経験が活用されるための社会的課題であると締めくくられました。

第2部のパネルディスカッションでは、内閣府の荻野秀明氏と本学経済経営学部の岡嶋裕子准教授(労働経済学)、澤田吉孝教授(金融論)の3人のパネリストによる、『令和6年度経済財政白書』に関する充実した議論が展開されました。
冒頭司会から、「失われた30年」と呼ばれる日本経済の長期停滞に加え、昨年には円安の影響もあってGDPでドイツに抜かれ世界第4位となり、世界経済における日本経済の相対的な地位が低下し続けてきたことがデータで示され、この30年間を振り返り「もし立ち返ることができるとしたならば、この“失われた30年”の長期停滞を回避できる最大のチャンスがどこにあったのか?」という問いに対して、荻野氏は、生産年齢人口が現在の中国のように減少局面にあった中で避けがたいものの、80年代から90年代にかけて、銀行への迅速な資本注入、過剰な設備の整理と産業転換(IT化の推進など)が出来ていれば、もう少し傷は浅かったのではないかとコメント。また、現在のインフレは、一次産品を中心とした輸入材の国際価格の上昇と円安による影響が大きく、インフレ率を超える名目賃金の上昇も実現されていない状況にあり、今後、輸入材価格の下落や円安の修正によってインフレ要因が取り除かれた場合の日本経済のデフレリスクを回避するために何が大切であるかとの問いに対しては、物価上昇だけはなく、持続的な賃金の上昇が重要であり、鉄道運賃など一部で引き続き硬直的なままになっているサービス価格など、人件費の持続的な上昇が当たり前となるノルムを出来るだけ多くの財・サービスに広げていくことが重要で、そのためには最低賃金の引き上げを一定ペース継続するなどの取り組みが必要であると述べました。
続いて、本学経済学科の岡嶋裕子准教授が、企業の人手不足感の解消に向けた女性の労働参加やリスキリング、労働移動と労働生産性の関係など、日本の労働市場の今日的課題について説明。労働力不足の解消の鍵となる女性の労働参加については、女性賃金の引き上げが必要との白書の指摘に加え、女性の労働参加の阻害要因となっている日本企業固有の雇用慣行である「メンバーシップ型雇用」の見直しや、昨今話題となっている税制や社会保障制度等の社会経済制度の見直しの必要性について解説しました。さらに、今年度の白書で取り上げられた外国人労働者や高齢者の活用についても、国として高技能外国人の戦略的活用の検討必要性や、働く意欲や能力がある高齢者に対して、年齢による差別や制限のないような社会および制度の設計についての問題提起がなされました。これに対して荻野氏は、従来のように男性が労働者のほとんどを占める時代から、人口減少の中で高齢者、女性、外国人といった様々なバックグラウンドや事情を持つ人が一緒に働くようになっている現状を踏まえ、誰もが働きやすい職場を企業・政府・労働者で協力して構築することが人口減少の中で社会の持続可能性を担保するのではないかとコメントしました。
また、本学の澤田吉孝教授は、家計の金融資産および住宅ストックの有効活用の重要性について説明。特に、高齢世代と若年層の抱える不安要素に焦点を当て、それぞれの課題と解決策を提示しました。高齢世代については、老後生活資金の不足や長寿化リスク、住居が広すぎるといった問題がある一方、金融資産や住宅資産が有効活用されていない現状を指摘。これに対し、住宅資産の流動化やリバースモーゲージ、リースバックといった仕組みが有効に活用できることが説明されました。その上で、老後の生活を支えるだけでなく、資産、特に預貯金を次世代へ円滑に移転する道筋についても説明されました。一方、若年世代では、将来の賃金・所得の見通しが立てにくいことや、ライフイベントへの支出の不透明感などが経済的不安を助長している点を指摘し、金融リテラシーの向上や構造的な賃上げなどの必要性を強調しました。荻野氏は、住居に関してはこれまで使ったら無くなってしまう消費財のように扱われていたが、若い世代を中心に中古住宅の忌避感も薄れている中で、他の金融資産と同様に、一つの資産としての有効活用を検討することは将来の選択肢を増やすうえで重要であるとコメント。また、転職の活発化や投資運用の積極化は将来の収入見通しの不確実性いわゆる不安の増幅につながることから、金融教育の推進を通して、将来収支見通しの不安を軽減し、賃上げを通じた将来収入期待を引上げる重要性は高いと言及されました。
また、第2部のディスカッションでは、「103万円の壁の引き上げは、短期的な人気取りのためのポピュリズム的政策提案であり、中長期的には非正規雇用の増大に結びつくのではないか?」といった質問や、移民受入れの伝統がある米国や欧州で移民排斥が政治的支持を生み出している海外情勢を踏まえて、「労働力人口が減少する日本は外国人労働力、そして移民の受入れに対して積極化しようとしているが、日本にとって本当に利益になるのか?」など参加者からの質問が取り上げられました。さらに、日本銀行出身の荻野氏に、デジタル通貨の拡大を踏まえ「通貨発行権を独占してきた中央銀行として、デジタル通貨の拡大が金融政策の有効性に与える影響はどの程度か?」といった質問もありました。こうした質問に対して、3人のパネリストはそれぞれの専門領域の視点から明瞭かつ説得力ある内容の回答し、非常に充実したパネルディカッションディスカッションとなりました。
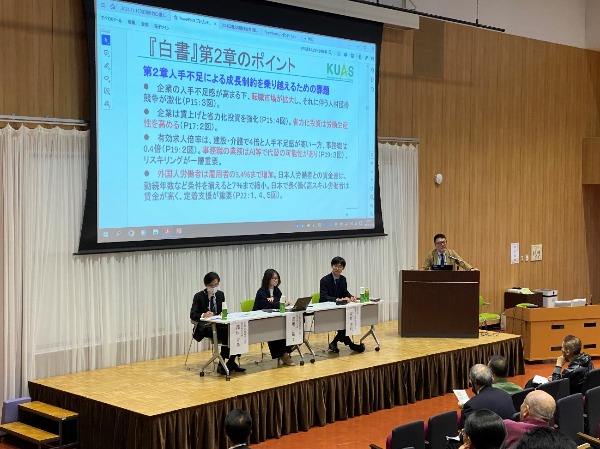
限られた時間の中では、多面的な分析を積み上げている『令和6年版経済財政白書』の詳細について触れることは困難であるにもかかわらず、参加者からは、「社会的関心の高い重要なポイントに絞り込んだ、大変に明瞭で説得力ある解説を聞くことができた」、「1つのテーマに対して複眼的に捉えることの重要性が理解できた」といった肯定的な声が多数寄せられました。
その他の意見も参考にしつつ、講演会のさらなる改善と継続開催を検討します。
今回参加頂いた方々および関係のみなさんに感謝いたします。
(経済経営学部教授 久下沼 仁笥)




